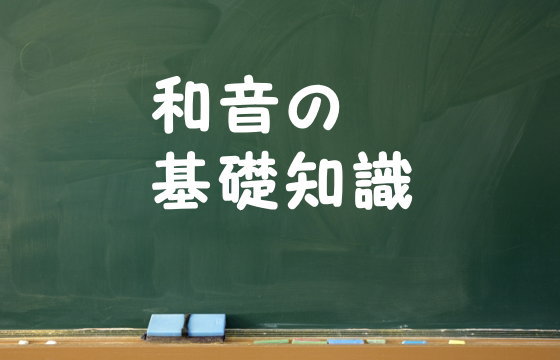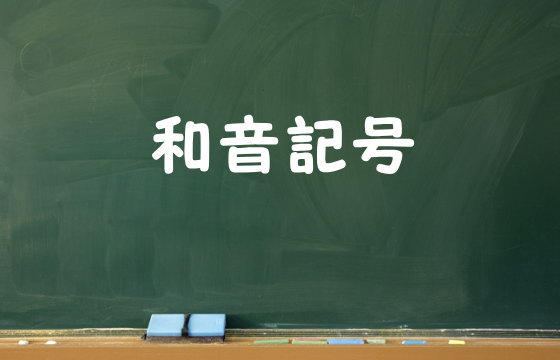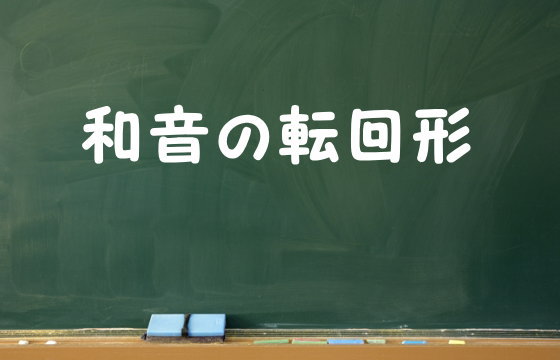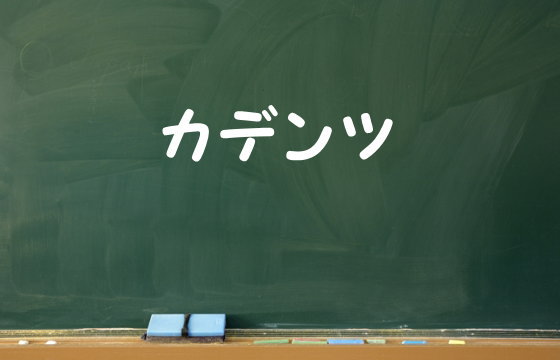メロディに付ける和音に正解はなく、人によって違ってきます。しかし、メロディに合う和音というのがあり、先ずはそれらを選ぶのが良いでしょう。メロディに合う和音の中でも、先ず最初に覚えるのが主要三和音(しゅようさんわおん)というもので、それらついて詳しく知っておきましょう。
主要三和音
大きな譜面を開く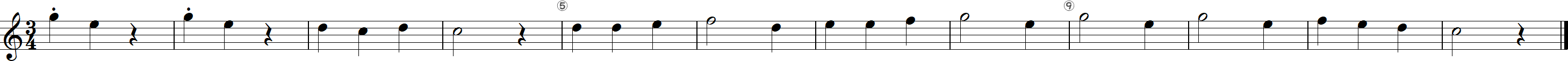
和音もハ長調から
上記はカッコウのメロディのみで、これに和音を付けていきましょう。このカッコウはハ長調なので、付ける和音もハ長調から作られる和音を使えば、メロディに合う和音となります。つまりはメロディを作っている音階から和音も作り、それを使うというのを基本、と考えておけば良いでしょう。
音階から作る和音とは?
和音は音階から3度ずつ、音を積み重ねて作られています。それについての詳細は同カテゴリの、和音の基礎知識から説明しています。
-
ハ長調の三和音 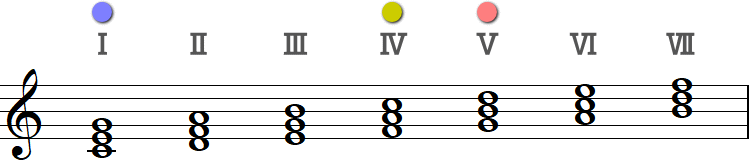
-
ハ長調の四和音 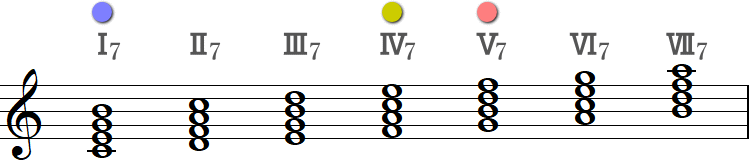
主要三和音は和音の中枢
①と②はハ長調の三和音と四和音です。両方とも1番目のⅠとⅠ7、4番目のⅣとⅣ7、5番目のⅤとⅤ7に目印が付いていますが、これら3種類が主要三和音と言われ、和音の中枢となります。主要三和音の順番は他の長調や短調でも、同じ1・4・5番目に作られます。主要三和音の特徴は以下の通りです。
- Ⅰ・Ⅰ7(主和音)
主和音(しゅわおん)は最も安定感があり、最初や最後に使う事が多いです。
- Ⅳ・Ⅳ7(下属和音)
下属和音(かぞくわおん)は自由な和音と言え、進行に広がりを作ります。
- Ⅴ・Ⅴ7(属和音)
属和音(ぞくわおん)は影の主役と言え、主和音に進行したがる性質があります。
和声は主要三和音が基本
楽曲の和音を分析すると、全て主要三和音のいずれかに分ける事が出来ます。和声(わせい)とは和音の進行を意味しますが、楽曲に上記で説明したような感じで、主要三和音を当てはめていけば、まともな和声を作ってくれます。次からは主要三和音のみで、カッコウに和声を付けてみましょう。
和音と和声とハーモニー
和音は「ド・ミ・ソ」や「レ・ファ・ラ」が単体で鳴ったもので、英語ではコードとも言われます。和声は「ド・ミ・ソ」や「レ・ファ・ラ」の和音の繋がりの事で、コード進行とも言います。そして、ハーモニーは和音と和声の両方の意味を持っています。
カッコウと主要三和音
-
カッコウの1~4小節目①(ハ長調) 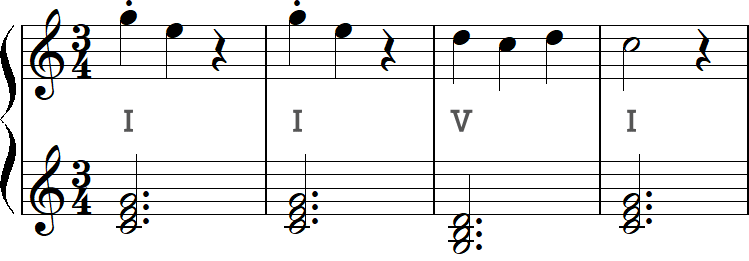
-
カッコウの1~4小節目②(ハ長調) 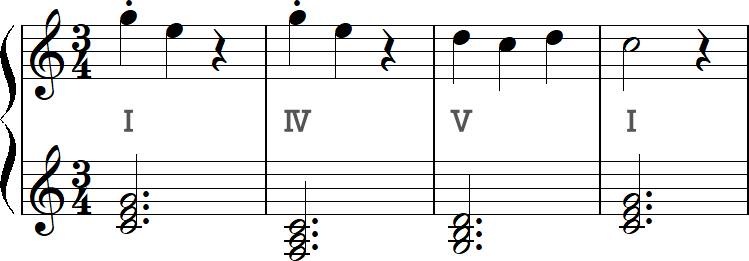
同じメロディで違う和音
上記はカッコウの1~4小節目です。①の2小節目はⅠですが、これを②ではⅣにしています。1・2小節目は同じメロディですが、和音を変える事も多々あります。もちろん、どちらが正解という事はなく、和音を付ける人の好みによります。
-
カッコウの1~4小節目③(ハ長調) 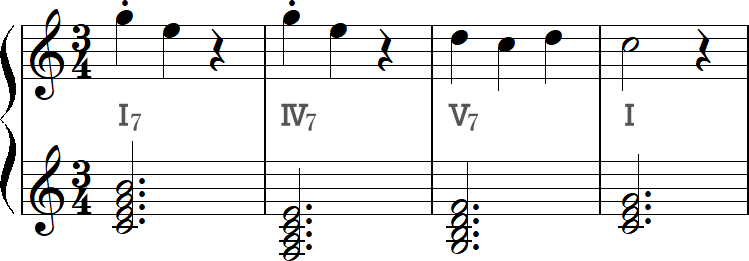
-
カッコウの1~4小節目④(ハ長調) 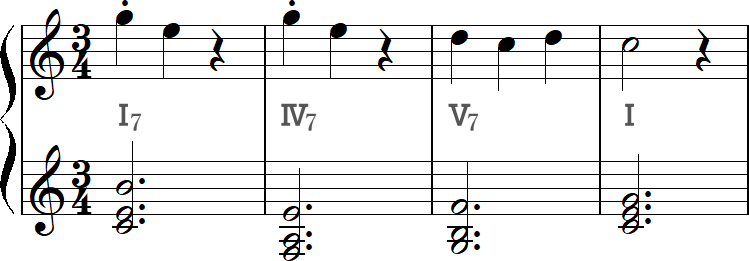
完全5度を省く
同じくカッコウの1~4小節目ですが、4小節目以外は四和音になっており、雰囲気も大きく変わると思います。③は四和音を全て使っていますが、④は完全5度を省いています。完全5度は和音の性格に大きな影響を及ぼさないので、省いて運指を簡潔にしたり、和音をシンプルに出来ます。
根音を省く時もある
合奏の時に根音を弾いてくれる演奏者が居れば、根音も省く事があります。演奏前に打合せをしたり、譜面があれば、他の演奏者の音を確認しておくと良いでしょう。
-
カッコウの5~8小節目⑤(ハ長調) 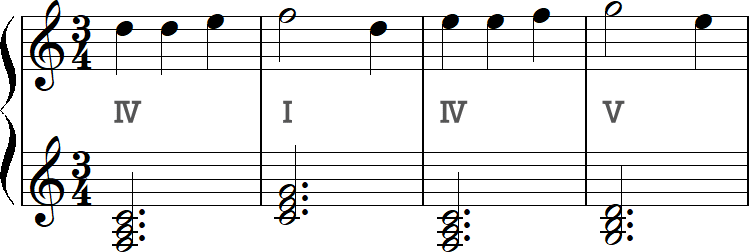
-
カッコウの5~8小節目⑥(ハ長調) 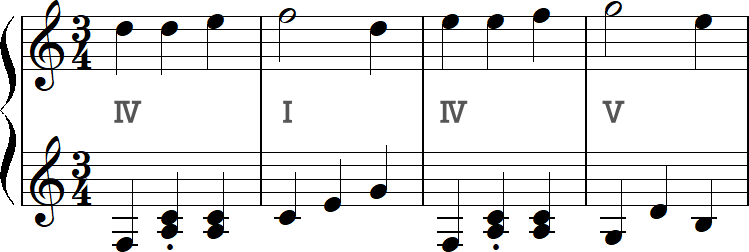
分散和音でも良し
次はカッコウの5~8小節目です。⑤はこれまで通り、和音を小節の頭で一気に鳴らしていますが、⑥のように分けて弾いてみるのも良いでしょう。こういった和音の使い方を分散和音(ぶんさんわおん)と言い、一気に和音を鳴らすのとは、また違う雰囲気を作れます。
-
カッコウの9~12小節目⑦(ハ長調) 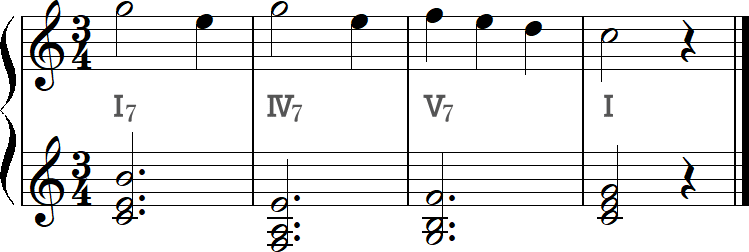
-
カッコウの9~12小節目⑧(ハ長調) 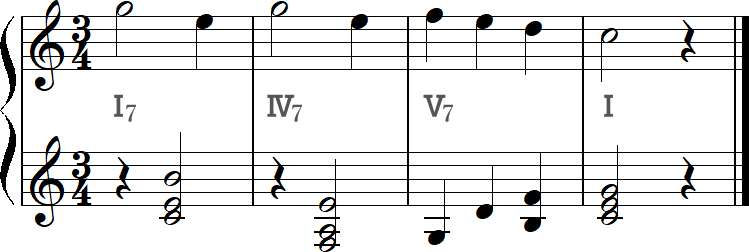
和音を2拍目から鳴らす
最後はカッコウの9~12小節目です。⑦の9・10小節目は四和音の完全5度抜きを、小節の頭から鳴らしていますが、⑧は1拍ずらして2拍目から鳴らしています。和音は小節の頭から鳴らさないといけない、という事もないので、時にはこんな風にしてやっても良いでしょう。
大きな譜面を開く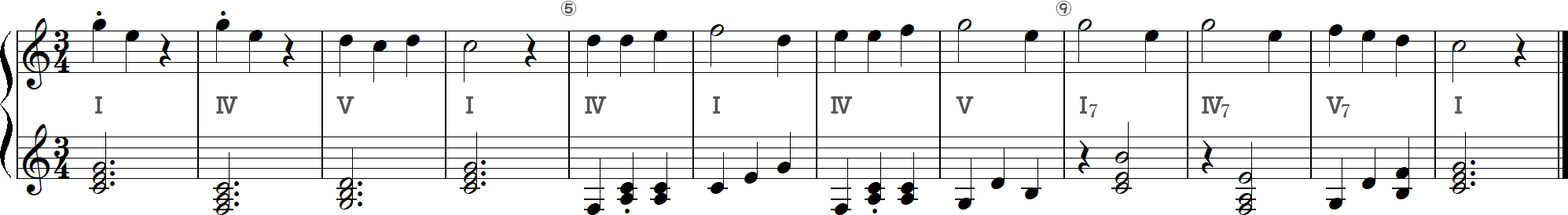
和声は人によりけり
和音を付けたカッコウを、12小節を通して聞いてみましょう。前述したように、主要三和音には特徴があるので、同じ曲に和音を付けるとしても、ある程度の和声は似るものの、人により異なったものになります。また、分散和音などを利用して、和音の鳴らし方を工夫するのも良いでしょう。
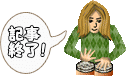
- 主和音・下属和音・属和音が主要三和音。
- 曲には主要三和音を当てはめれば形にはなる。
- 和音をバラして弾く事を分散和音と言う。