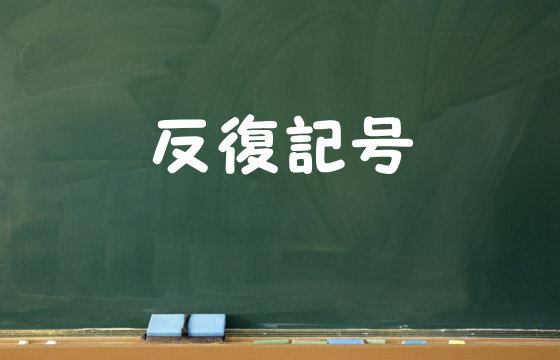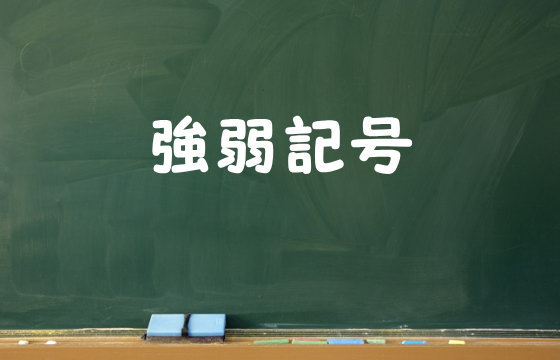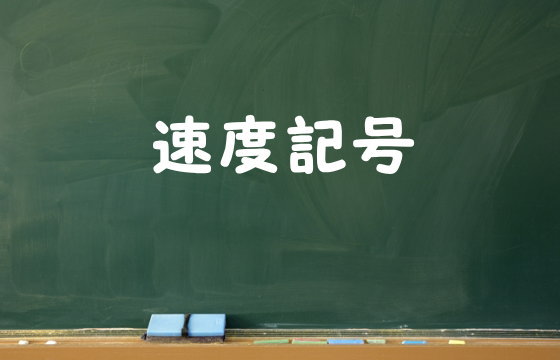フレーズに飾り付けをして、洒落た音にする事を装飾音(そうしょくおん)と言います。細かくは装飾音符と装飾記号に分けられますが、特に気にする事はありません。しかし、この装飾音には明確な決まりがなく、楽典や国によっても説明の違いが見られます。
打音
-
長前打音 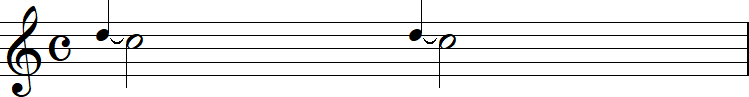
-
長前打音の鳴らし方 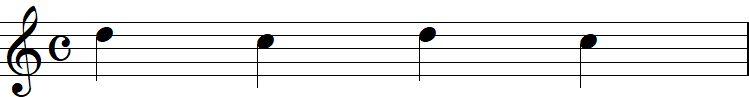
長前打音は見た目通り
①に見られる小さ目の4分音符を長前打音(ちょうぜんだおん)と言います。長前打音は見た目通り4分音符の長さにする事が多く、実際には②のように演奏します。
打音の特徴
打音は小さ目の音符にする事と、どれだけ高音になっても棒は上向きにする、というのが特徴です。
-
短前打音 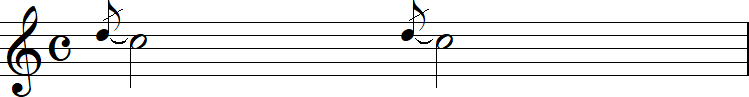
-
短前打音の鳴らし方④ 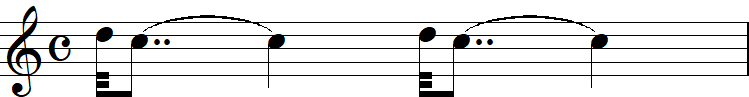
-
短前打音の鳴らし方⑤ 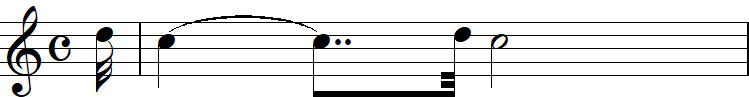
短前打音の弾き始め
③に見られる斜線入りの8分音符を短前打音(たんぜんだおん)と言います。弾き始めが③の2分音符と同じ④の時もあれば、それより少し前になる⑤の時もあります。短全打音は出来るだけ短く弾く、というのがよく見られる説明ですが、上記で示す32分音符より、多少は長くなっても問題はありません。
-
中間打音 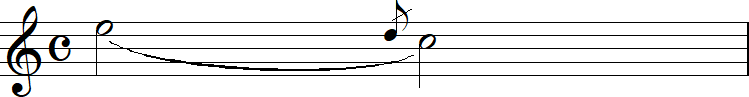
-
中間打音の鳴らし方⑦ 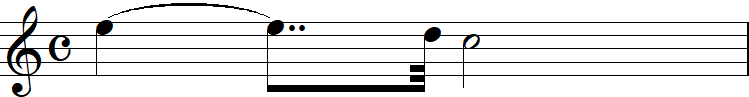
中間打音は二音の間
⑥の2分音符の間に見られる、斜線入りの8分音を中間打音(ちゅうかんだおん)と言います。⑦で見られるように、ここでも32分音符で表していますが、多少の誤差はあっても良いでしょう。
-
後打音 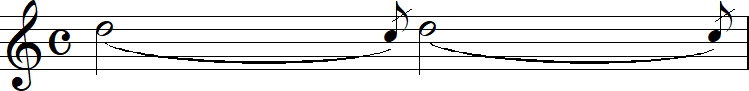
-
後打音の鳴らし方⑨ 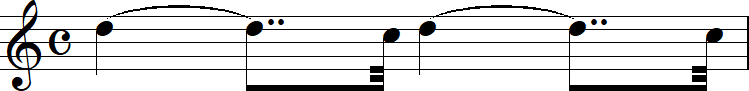
後打音は後ろ
⑧に見られる2分音符に続く、斜線入りの8分音符を後打音(こうだおん)と言います。呼び方では区別されますが、中間打音とよく似ているかと思います。
-
複前打音 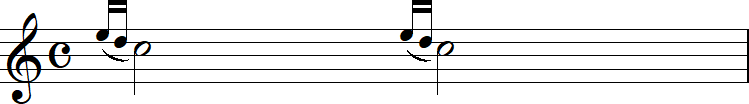
-
複前打音の鳴らし方⑪ 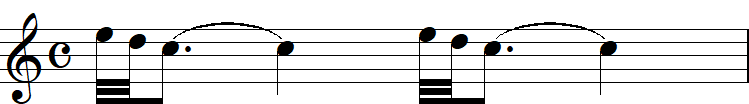
-
複前打音の鳴らし方⑫ 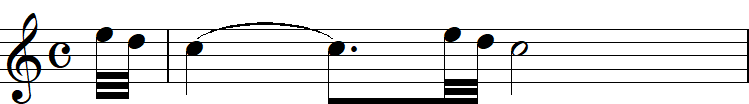
複前打音の弾き始め
⑩で見られる16分音符の連なりを複前打音(ふくぜんだおん)と言います。短前打音がそうであったように、複前打音の弾き始めも⑩の2分音符と同じ⑪であったり、少し前の⑫であったりもします。また、この後にも説明する、複が付く打音には斜線を必要としません。
-
複中間打音 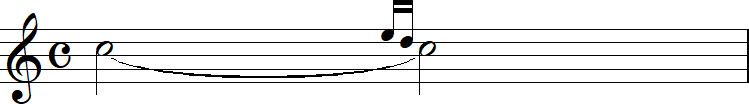
-
複中間打音の鳴らし方⑭ 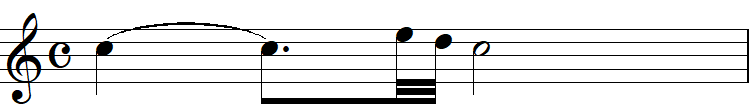
複中間打音は二音の間
⑬の2分音符の間に見られるのが複中間打音(ふくちゅうかんだおん)です。前の複前打音もそうですが、複が付く打音は16分音符で記されますが、実際には16分音符より短く演奏される事が多いです。しかし、これはテンポによっても左右されるので、見た目のまま16分音符で演奏される事もあります。
-
複後打音 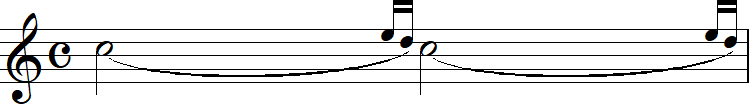
-
複後打音の鳴らし方⑯ 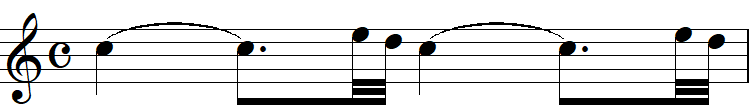
複後打音は後ろ
⑮で見られるのが複後打音(ふくこうだおん)です。後打音と中間打音の時と同じく、複後打音も複中間打音とよく似ているのが分かります。
打音の解釈も様々
冒頭でも説明しましたが、装飾音である打音の解釈も様々なので、可能ならば音源を聞いたり、作曲者に尋ねるのが確実です。それは下記の装飾音でも、同じ事が言えます。
トリル・プラルトリラー・モルデント・トレモロ
-
トリル 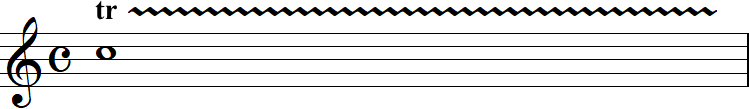
-
トリルの弾き方② 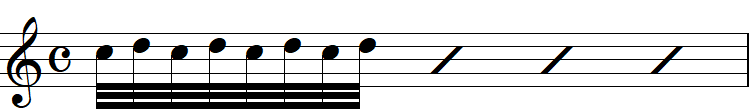
-
トリルの弾き方③ 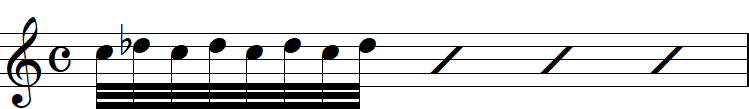
-
トリルの弾き方④ 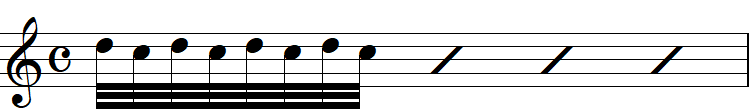
トリルは隣の音
①のtrをトリルと言い、その音と隣の音とを交互に素早く鳴らします。②が多く見られるトリルですが、③のように半音隣り合わせでも良いです。その場合はtr♭というように記される事もあります。また、④のように高い音から弾き始める、という場合もあります。
-
プラルトリラー(プララー) 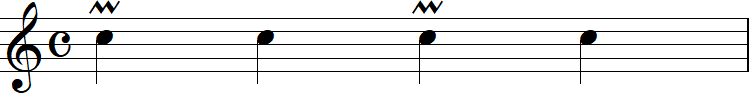
-
プラルトリラー(プララー)の弾き方⑥ 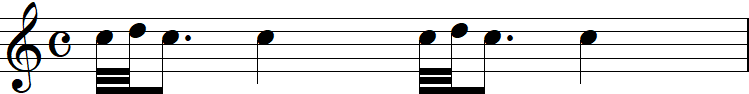
プラルトリラーは高い音
⑤に見られるギザギザの短い波線をプラルトリラー(プララー)と言います。トリルは連続で繰り返しましたが、プラルトリラーは⑥のように、高い音を1回だけ挟みます。
-
モルデント 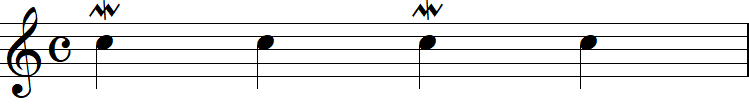
-
モルデントの弾き方⑧ 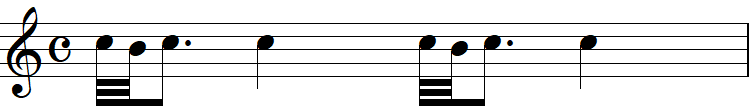
モルデントは低い音
⑦で見られるプララーに縦線を加えたものをモルデントと言います。プララーが高い音だったのに対し、モルデントは低い音を1回だけ挟みます。
-
トレモロ 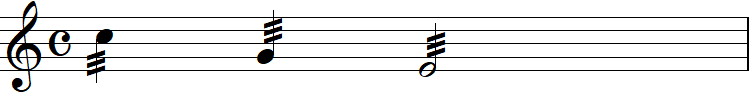
-
トレモロの弾き方⑩ 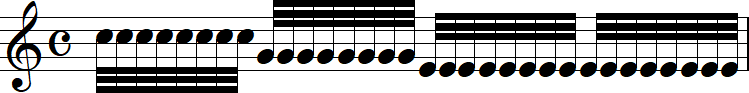
トレモロは同じ音
⑨で見られる音符の棒に斜線が入ったものをトレモロと言います。トレモロは⑩のように、その音だけを素早く繰り返します。トレモロの斜線は2本の場合もあります。
ターン・アルペジオ
-
ターン(音符の上A) 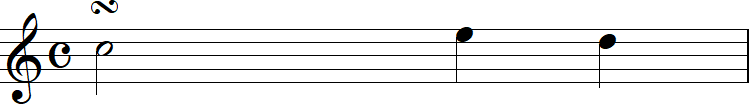
-
ターン(音符の上A)の弾き方② 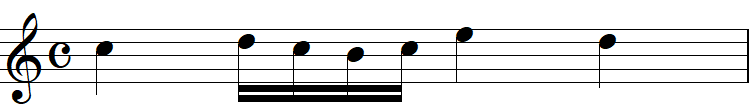
ターン(その1)
①で見られる2分音符の上にある記号をターンと言い、その音符の上下を囲むようにして弾くので、②のような感じになります。しかし、このターンの表現はややこしく、何通りかあります。
-
ターン(音符の間A) 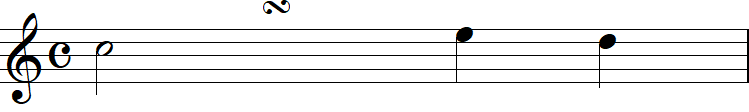
-
ターン(音符の間A)の弾き方④ 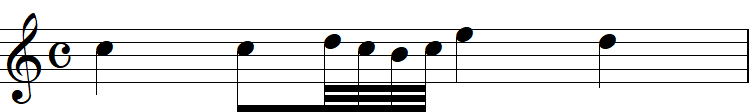
ターン(その2)
③のように音符の間に記すターン記号もあり、その場合は④のような感じで弾く事が多いです。
-
ターン(音符の上B) 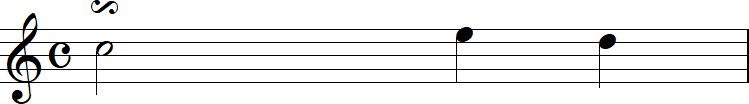
-
ターン(音符の上B)の弾き方⑥ 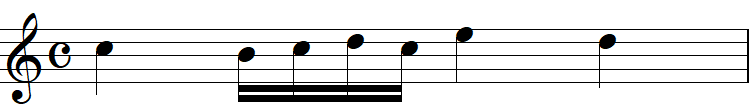
ターン(その3)
⑤のターン記号ですが、前の2つを反転させたターン記号になっています。これが2分音符の上にあると、⑥のような感じで弾く事が多いです。
-
ターン(音符の間B) 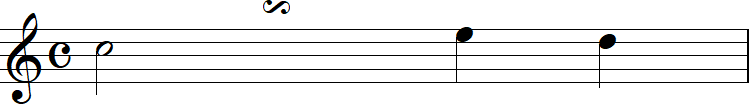
-
ターン(音符の間B)の弾き方⑧ 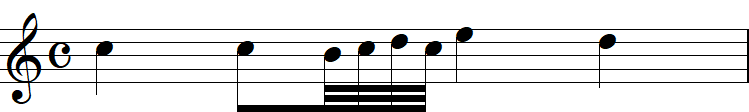
ターン(その4)
最後は先程のターン記号が⑦のように、音符の間に移動しています。そうなると、⑧のように弾く事が多いでしょうか。
ターンは自由に弾こう
ターンの解釈が最も難しく、楽典でも説明が異なっています。上下の音で取り込むように弾く、というのは共通しているので、どのターンが出てきても、それさえ守れば自由に弾いても良いかと思います。
-
アルペジオ 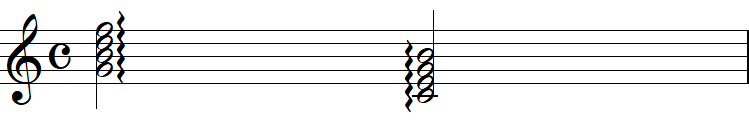
-
アルペジオの弾き方⑩ 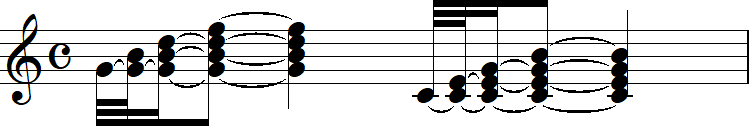
アルペジオはずらして弾く
⑨で見られる音符玉に添う縦の波線をアルペジオと言い、一音ずつを少しずらして弾く事を意味するので、⑩のような感じになります。アルペジオはコードを弾く時に、用いられる事が多いでしょう。
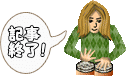
- 打音は小さい音符で棒は上向き。
- プラルトリラーとモルデントはトリルの単数形。
- ターンの解釈が最も複雑と思われる。