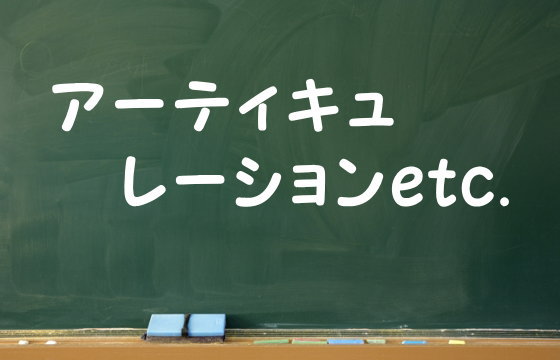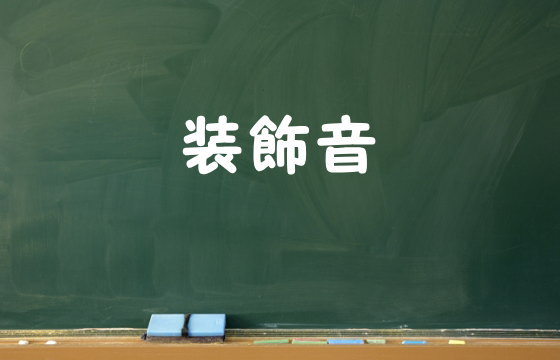音の大きさを決めるのが強弱記号です。強弱記号はポピュラー音楽の譜面にはあまり見られず、クラシック音楽でよく使用され、イタリア語で表現されています。強弱記号にもたくさんの種類がありますが、ここでは基本的なものだけを見ていく事にしましょう。
強弱記号①
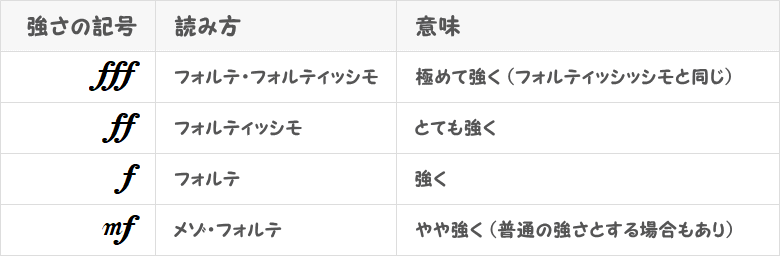
フォルテ系は強い音
強くを意味するのが![]() のフォルテです。それが重なる毎に強さが増し、ここでは
のフォルテです。それが重なる毎に強さが増し、ここでは![]() までしか表記していませんが
までしか表記していませんが![]() もあり、読み方はフォルテ・フォルテ・フォルティッシモと言います。やや強くと表現される事の多い
もあり、読み方はフォルテ・フォルテ・フォルティッシモと言います。やや強くと表現される事の多い![]() ですが、これを普通の強さとする場合もあります。
ですが、これを普通の強さとする場合もあります。
フォルティッシッシモとは?
以前は![]() をフォルティッシッシモとも呼んでいましたが、現在ではフォルテ・フォルティッシモと呼ぶのが普通です。
をフォルティッシッシモとも呼んでいましたが、現在ではフォルテ・フォルティッシモと呼ぶのが普通です。![]() を基準に
を基準に![]() が増える毎に、フォルテという呼び方を重ねるわけです。
が増える毎に、フォルテという呼び方を重ねるわけです。
 (フォルティッシモ)
(フォルティッシモ) (フォルテ・フォルティッシモ)
(フォルテ・フォルティッシモ) (フォルテ・フォルテ・フォルティッシモ)
(フォルテ・フォルテ・フォルティッシモ)
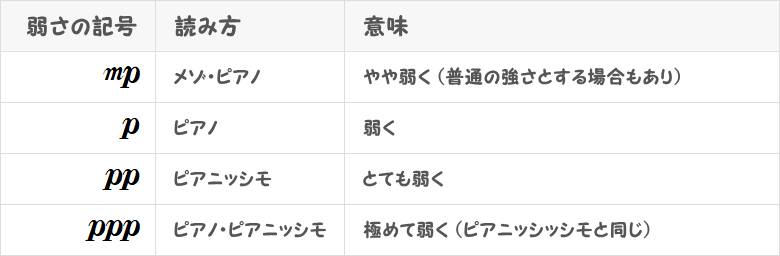
ピアノ系は弱い音
弱くを意味するのが![]() のピアノです。それが重なる毎に更に弱くなり、上記の
のピアノです。それが重なる毎に更に弱くなり、上記の![]() より弱い
より弱い![]() もあり、読み方はピアノ・ピアノ・ピアニッシモと言います。やや弱くと表現される事の多い
もあり、読み方はピアノ・ピアノ・ピアニッシモと言います。やや弱くと表現される事の多い![]() ですが、静かめの曲なら普通の強さとする場合もあるでしょう。
ですが、静かめの曲なら普通の強さとする場合もあるでしょう。
ピアニッシッシモとは?
以前は![]() をピアニッシッシモと呼んでいましたが、現在ではピアノ・ピアニッシモと呼ぶのが普通でしょう。
をピアニッシッシモと呼んでいましたが、現在ではピアノ・ピアニッシモと呼ぶのが普通でしょう。![]() を基準に
を基準に![]() が増える毎に、ピアノという呼び方を重ねるわけです。
が増える毎に、ピアノという呼び方を重ねるわけです。
 (ピアニッシモ)
(ピアニッシモ) (ピアノ・ピアニッシモ)
(ピアノ・ピアニッシモ) (ピアノ・ピアノ・ピアニッシモ)
(ピアノ・ピアノ・ピアニッシモ)
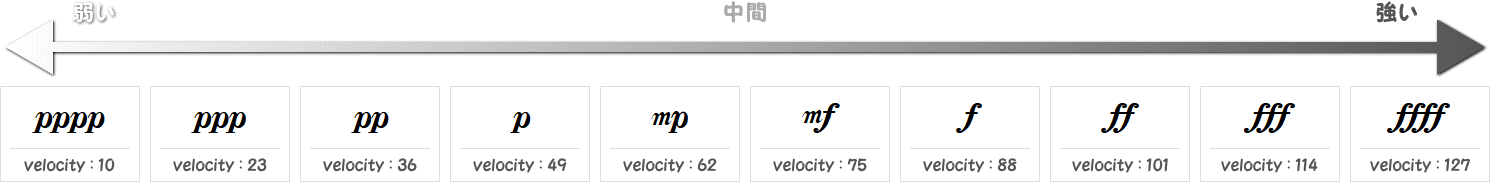
ベロシティについて
音楽を作るアプリにはベロシティ(velocity)という用語があります。英和辞典では主に「速度」と載っていますが、音楽アプリのベロシティは音の大きさを、数値やグラフで表したものです。強弱記号をベロシティで表す事などありえませんが、強いて表すなら上記のような感じでしょうか。
ベロシティの基準は変わる
ベロシティの最大数は127で、それを![]() としてみると、中間の
としてみると、中間の![]() と
と![]() は62~75位になるでしょうか。曲の雰囲気などでも基準は変わってくるので、ベロシティ数値は大体の目安として考えてください。
は62~75位になるでしょうか。曲の雰囲気などでも基準は変わってくるので、ベロシティ数値は大体の目安として考えてください。
強弱記号の真ん中は?
強弱記号には真ん中を表すものがありません。楽典によっては![]() を真ん中とするものもありますが、曲によっては
を真ん中とするものもありますが、曲によっては![]() を真ん中にする事もあり、使い分けるのが良いでしょう。
を真ん中にする事もあり、使い分けるのが良いでしょう。
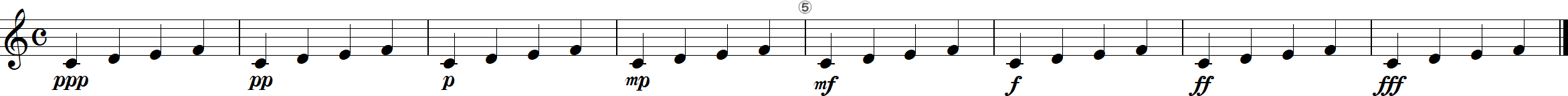
強弱記号の効果
強弱記号は音符の直下に書くのが基本ですが、無理な場合は音符の直近に書けば良いでしょう。強弱記号は書かれた音符から、後の音符にも効果が持続します。上記の8小節だと、1小節ずつ異なる強弱記号の効果がある、という事になります。
強弱記号②
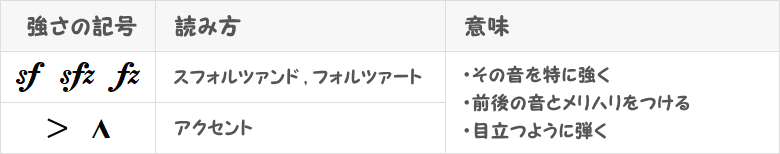
指定の音だけを強く弾く
![]() と
と![]() をスフォルツァンド、
をスフォルツァンド、![]() をフォルツァートと言いますが、読み方は楽典によって微妙に違ってきます。>とΛをアクセントと言い、これらは全て強く弾くという意味なので、フォルテ系の仲間ですが、指定された音だけを強く弾きます。
をフォルツァートと言いますが、読み方は楽典によって微妙に違ってきます。>とΛをアクセントと言い、これらは全て強く弾くという意味なので、フォルテ系の仲間ですが、指定された音だけを強く弾きます。
-
ピアニッシモからスフォルツァンド 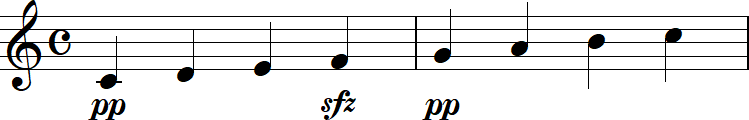
-
メゾ・フォルテからスフォルツァンド 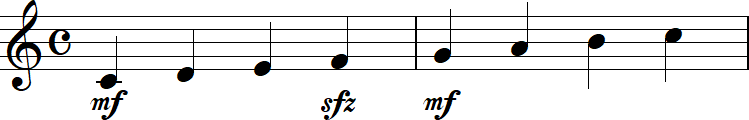
強さの違うスフォルツァンド
①は周辺の音符が![]() で、②は周辺の音符が
で、②は周辺の音符が![]() で、両方とも1小節目の終わりに
で、両方とも1小節目の終わりに![]() があります。同じ
があります。同じ![]() ですが、周辺の音符の強さが異なるため、強さの違う
ですが、周辺の音符の強さが異なるため、強さの違う![]() になります。曲の流れに合わせた
になります。曲の流れに合わせた![]() にしてやりましょう。
にしてやりましょう。
強弱記号③
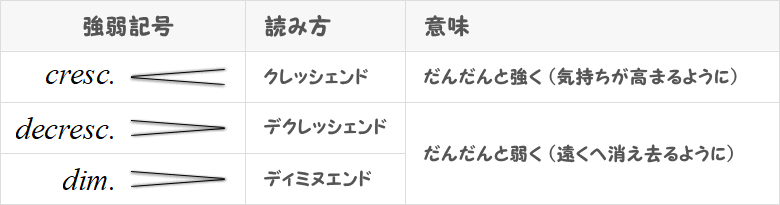
少しずつ変化する
少しずつ変化する強弱記号もあり、だんだんと強くをクレッシェンド、逆に、だんだんと弱くをデクレッシェンドかディミヌエンドと言います。表にも記すように、文字か記号での書き方があります。
-
cresc.とdim.(文字表記) 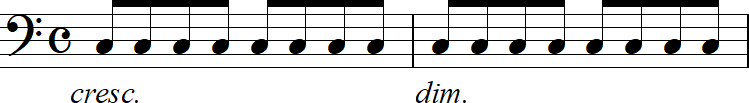
-
cresc.とdim.(記号表記) 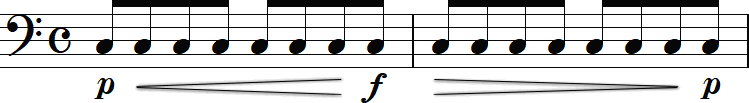
強弱記号で指定する
どちらかと言えば①より②の、記号を使ったクレッシェンドやディミヌエンドの方がよく見られ、感覚的にも分かり易いかと思います。記号の場合は![]() や
や![]() 等を使い、強弱を指定してやると親切でしょう。
等を使い、強弱を指定してやると親切でしょう。
-
1音ずつのクレッシェンド 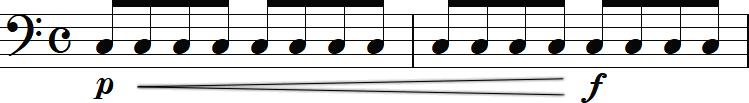
-
4音ずつのクレッシェンド 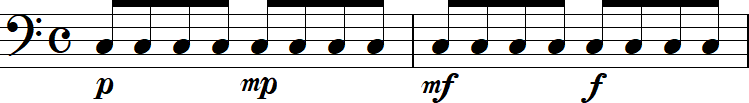
クレッシェンドの表現
例えば③のようなクレッシェンドだと、![]() までの1音ずつを異なる音量で弾くのが理想ですが、これは中々に難しい表現です。そこで④のように、4音ずつに区切って音量を上げていくと、弾き易くなるかもしれません。クレッシェンドの表現にも、個人差が出てくると思います。
までの1音ずつを異なる音量で弾くのが理想ですが、これは中々に難しい表現です。そこで④のように、4音ずつに区切って音量を上げていくと、弾き易くなるかもしれません。クレッシェンドの表現にも、個人差が出てくると思います。
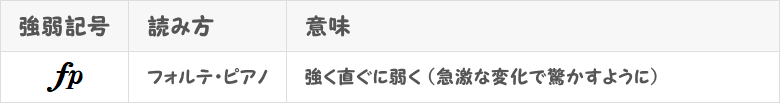
フォルテ+ピアノ
![]() と
と![]() が合わさった
が合わさった![]() という強弱記号もあり、読み方はフォルテ・ピアノで、強く直ぐに弱くという意味です。ストリングス系の弦楽器などで、使われる事が多いと思います。
という強弱記号もあり、読み方はフォルテ・ピアノで、強く直ぐに弱くという意味です。ストリングス系の弦楽器などで、使われる事が多いと思います。
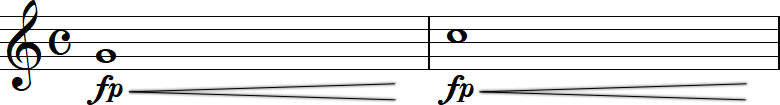
一瞬だけ大きな音
![]() だけという場合もありますが、クレッシェンドと一緒に使われる事もあります。拍の頭だけ音が大きくなっているのが、聞き取れると思います。
だけという場合もありますが、クレッシェンドと一緒に使われる事もあります。拍の頭だけ音が大きくなっているのが、聞き取れると思います。
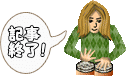
- フォルテ系は強く、ピアノ系は弱く。
- スフォルツァンドetc.は特定の音を強く弾く。
- 少しずつや急に変化する強弱記号もある。