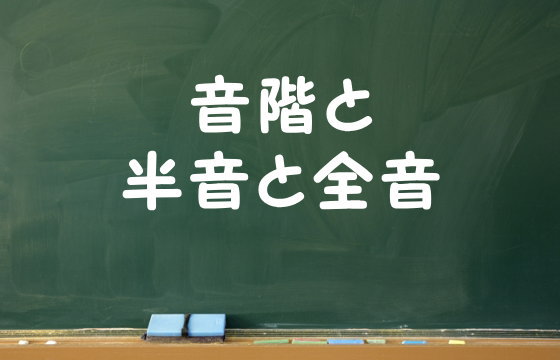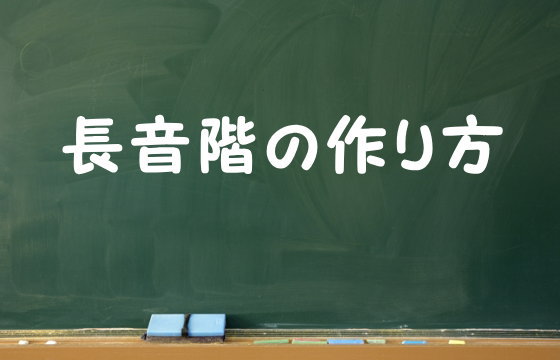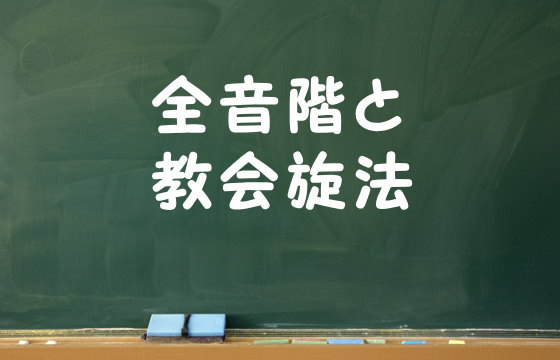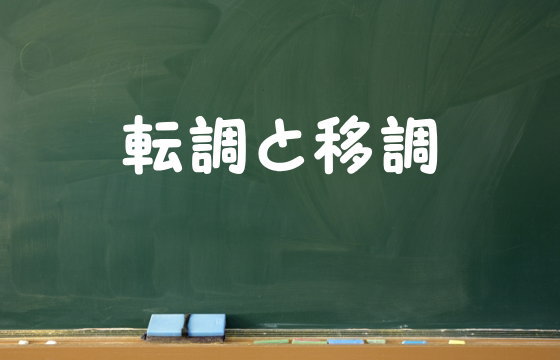曲には基本となる音の高さがあり、それを調(ちょう)や、英語式にはKey(キー)と言ったりします。このカテゴリでも説明してきた、色んな種類の長調と短調の事と思ってもらえば良く、それを簡潔に示すものを調号(ちょうごう)と言います。
#と♭の調号
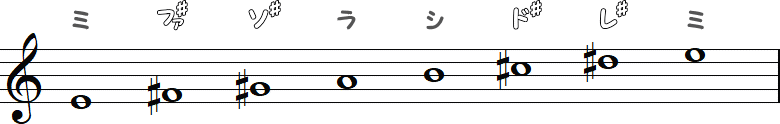
臨時記号で表すホ長調
例えば、ホ長調を表すには上記のように、一音ずつに#の臨時記号を付けても表せます。しかし、その度に#を書くのは面倒なので、ホ長調は次のようにして表すのが通常です。
-
ホ長調の調号 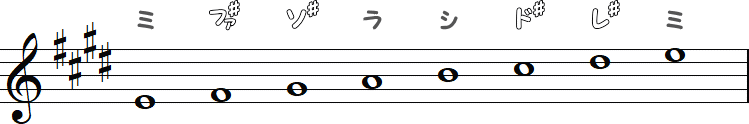
-
嬰ハ短調の調号 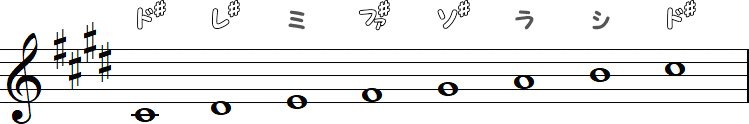
調号で表すホ長調と嬰ハ短調
①はト音記号の直ぐ右隣に#が4つあり、こういったものを調号と言います。五線のファ・ソ・ド・レの高さに#が記されており、オクターブがどれだけ違っても、それら4つの音には#が付きます。また、#が4つの調号はホ長調の平行短調である、②の嬰ハ短調も同時に表しています。
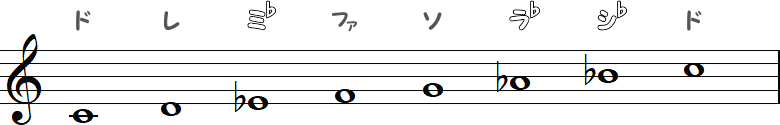
臨時記号で表すハ短調
ハ短調を表すには上記のように、一音ずつに♭の臨時記号を付けても表せます。やはり、それでは手間がかかるので、ハ短調は次のようにして表すのが普通です。
-
ハ短調の調号 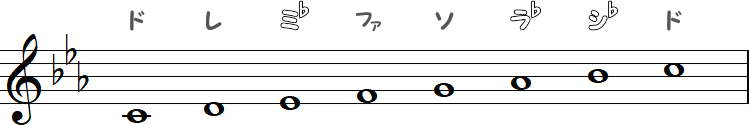
-
変ホ長調の調号 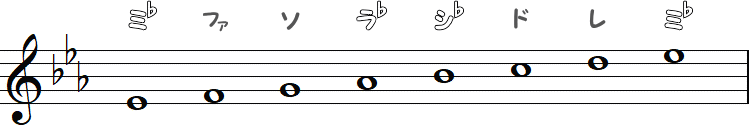
調号で表すハ短調と変ホ長調
③はト音記号の右隣に♭が3つあり、やはりこれも調号です。五線のミ・ラ・シの高さに♭が記されており、やはりオクターブがどれだけ違っても、それら3つの音に♭が付きます。そして、♭が3つの調号はハ短調の平行長調である、④の変ホ長調も同時に表しています。
調号は7種類ずつ
#の調号は7種類、♭の調号も7種類あり、全部で14種類の調号があります。#と♭の調号を、一通り確認しておきましょう。
-
ハ長調(Cメジャー)/ イ短調(Aマイナー) 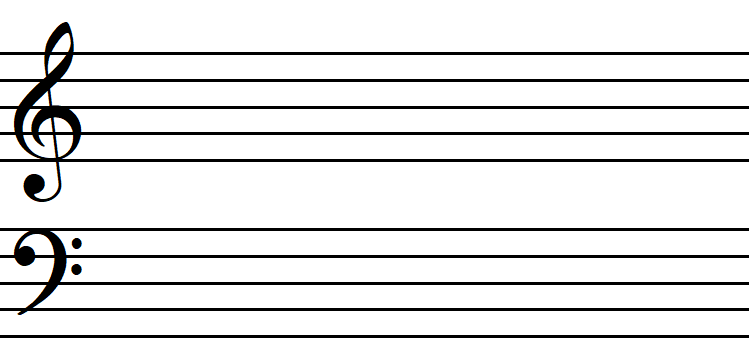
-
ト長調(Gメジャー)/ ホ短調(Eマイナー) 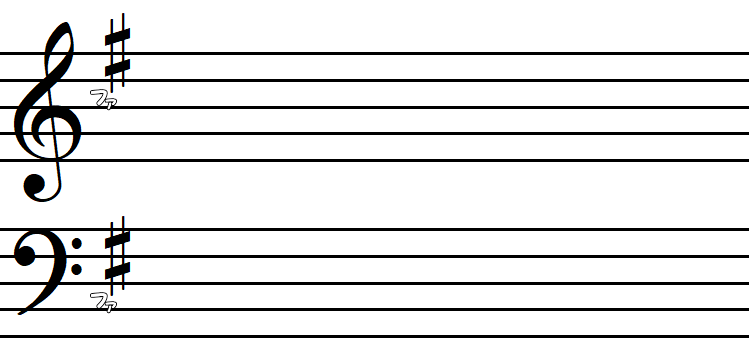
-
ニ長調(Dメジャー)/ ロ短調(Bマイナー) 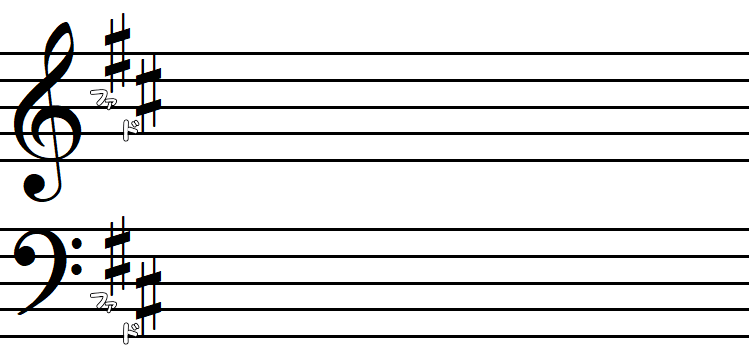
-
イ長調(Aメジャー)/ 嬰ヘ短調(F#マイナー) 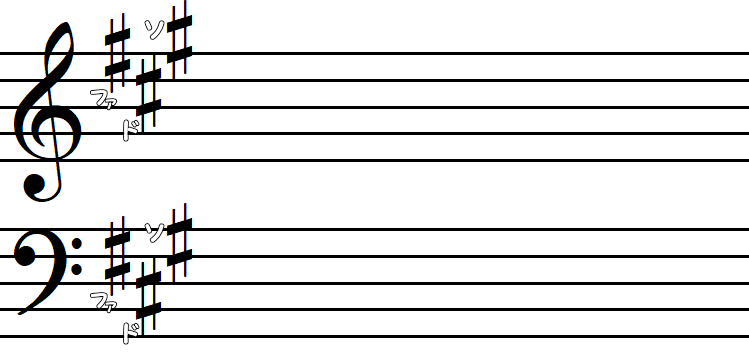
-
ホ長調(Eメジャー)/ 嬰ハ短調(C#マイナー) 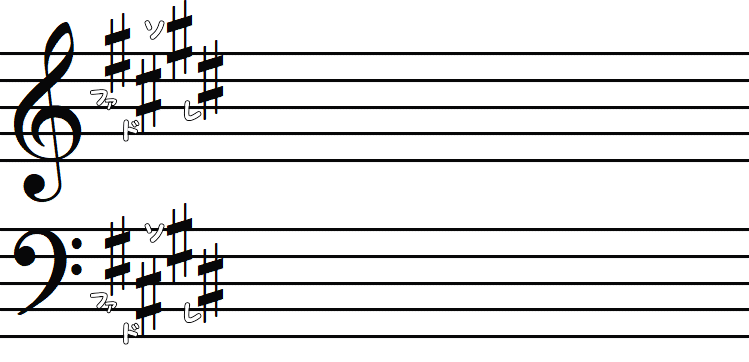
-
ロ長調(Bメジャー)/ 嬰ト短調(G#マイナー) 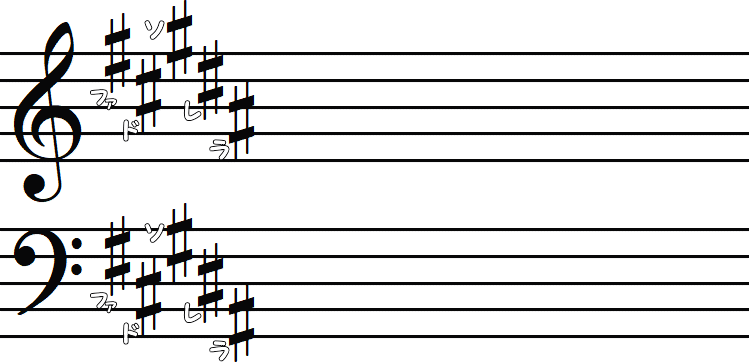
-
嬰ヘ長調(F#メジャー)/ 嬰ニ短調(D#マイナー) 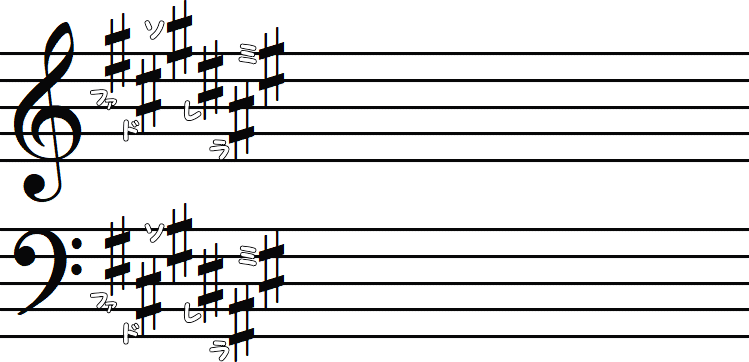
-
嬰ハ長調(C#メジャー)/ 嬰イ短調(A#マイナー) 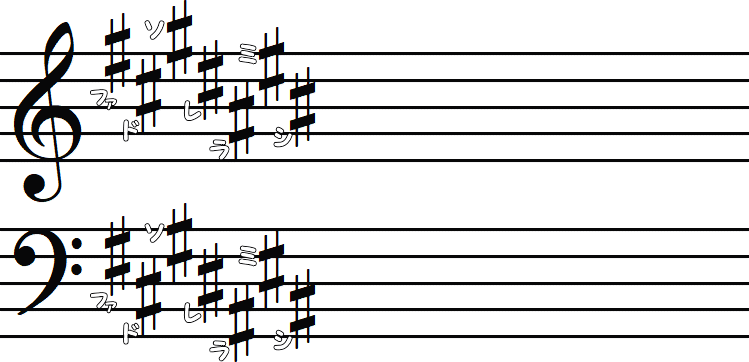
#の調号が付く順番
#の調号は「ファ・ド・ソ・レ・ラ・ミ・シ」という順に付いていきます。調号はト音記号だけでなく、ヘ音記号にも付くので、必要に応じて確認しておきましょう。
-
ハ長調(Cメジャー)/ イ短調(Aマイナー) 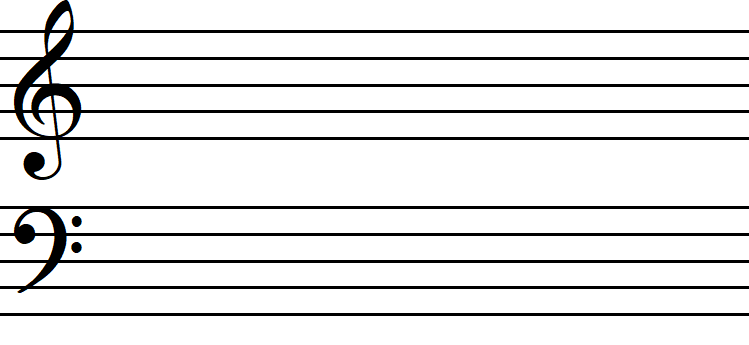
-
ヘ長調(Fメジャー)/ ニ短調(Dマイナー) 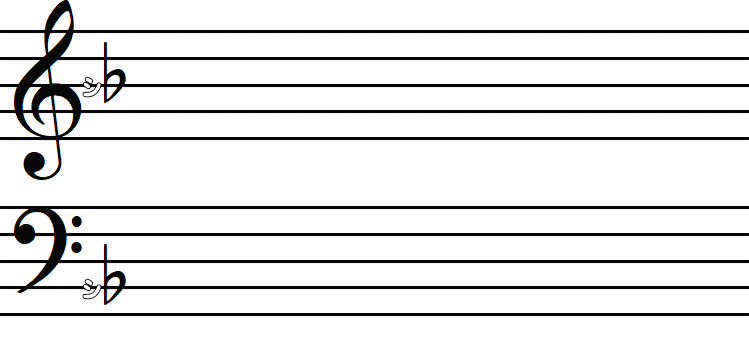
-
変ロ長調(B♭メジャー)/ ト短調(Gマイナー) 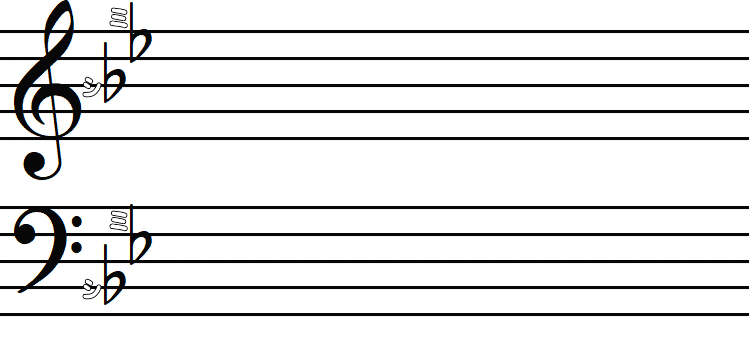
-
変ホ長調(E♭メジャー)/ ハ短調(Cマイナー) 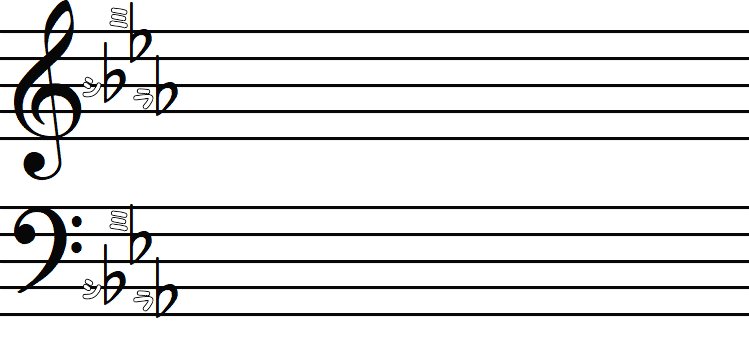
-
変イ長調(A♭メジャー)/ ヘ短調(Fマイナー) 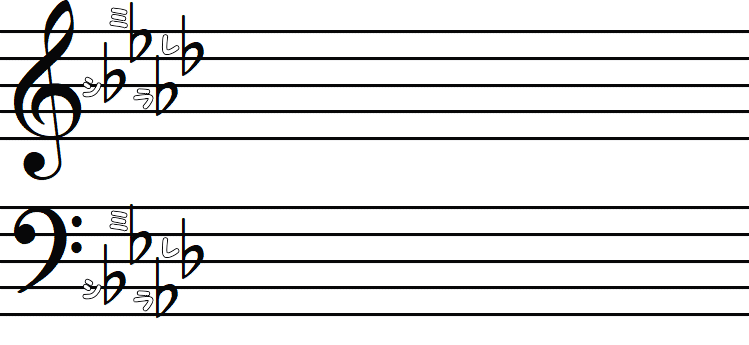
-
変ニ長調(D♭メジャー)/ 変ロ短調(B♭マイナー) 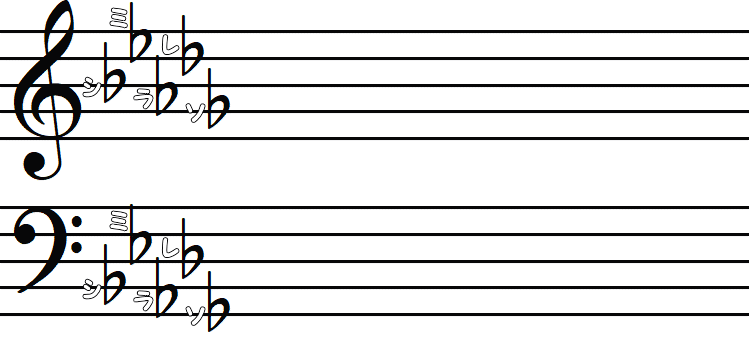
-
変ト長調(G♭メジャー)/ 変ホ短調(E♭マイナー) 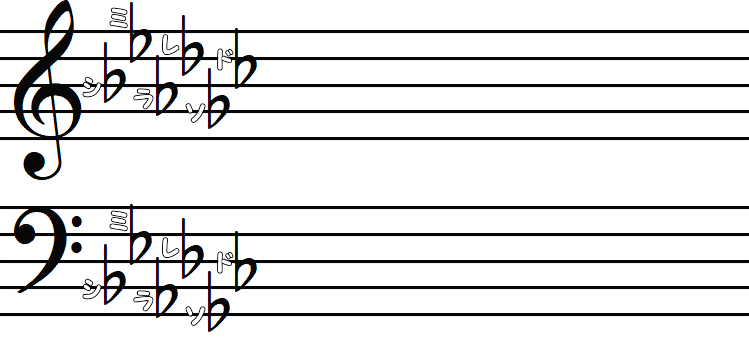
-
変ハ長調(C♭メジャー)/ 変イ短調(A♭マイナー) 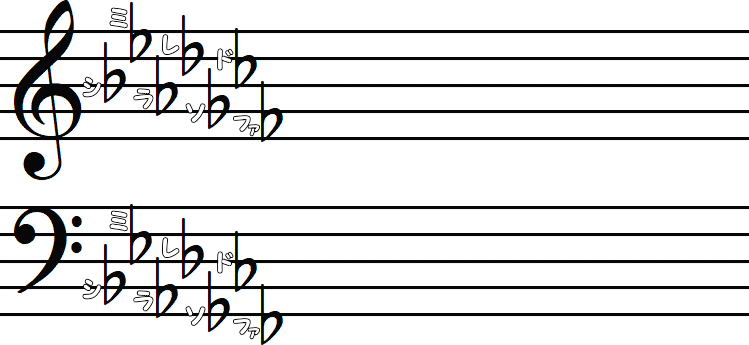
♭の調号が付く順番
♭の調号は「シ・ミ・ラ・レ・ソ・ド・ファ」という順に付いていきます。これは#の調号とは、逆の順番になっています。
調は24通り
調は全部で30通りありますが、長調は嬰ヘ長調と変ト長調、嬰ハ長調と変ニ長調、変ハ長調とロ長調、短調は嬰ニ短調と変ホ短調、嬰イ短調と変ロ短調、変イ短調と嬰ト短調、の6通りが異名同音の関係になるので、調は全部で24通りと考えられます。
調号の覚え方(シャープ編)
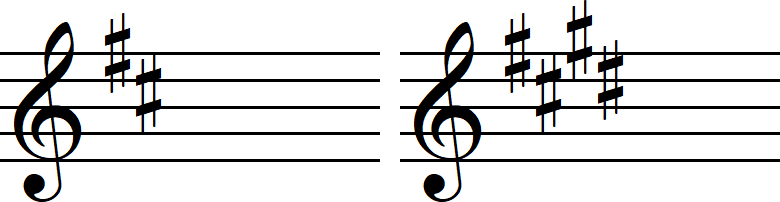
#の調号を探る
上記は#が2つと4つの調号ですが、何の調か直ぐに思い出せない事もあります。探りながら何の調か分かる方法が昔からあるので、これら2種類を例に挙げて説明していきます。
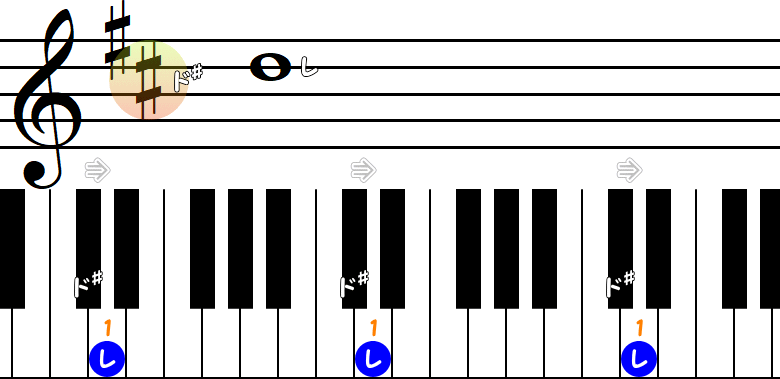
#2つの長調
一番右の#に注目しましょう。ドの高さに#があるので、つまりはド#という事です。そのド#から半音1つ上の音はレで、そのレが長調の主音になるので、#2つの調号はニ長調と判断できます。
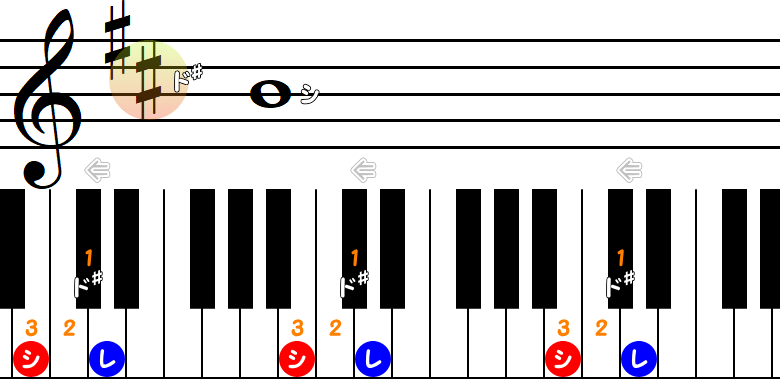
#2つの短調
次は#2つの短調を求めます。長調の主音であるレから、半音3つ下はシです。そのシが短調の主音になるので、#2つの短調はロ短調という事になります。
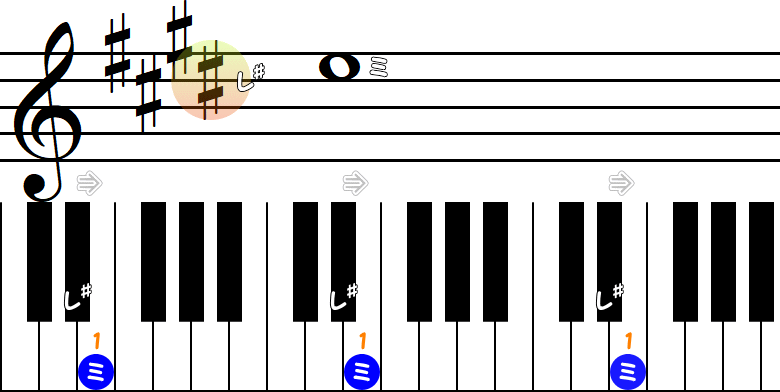
#4つの長調
やはり一番右の#に注目してください。レの高さに#があるので、これはレ#という事です。そのレ#から半音1つ上の音はミで、そのミが長調の主音になるので、#4つの調号はホ長調と判断できます。
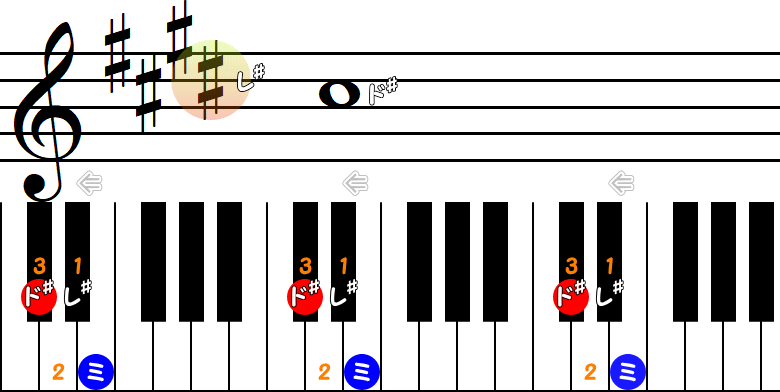
#4つの短調
次は#4つの短調を求めます。長調の主音であるミから、半音3つ下はド#です。そのド#が短調の主音になるので、#4つの短調は嬰ハ短調という事になります。
#の調号の覚え方まとめ
- 一番右の#から半音上が長調の主音。
- 長調の主音から半音3つしたが短調の主音。
調号の覚え方(フラット編)
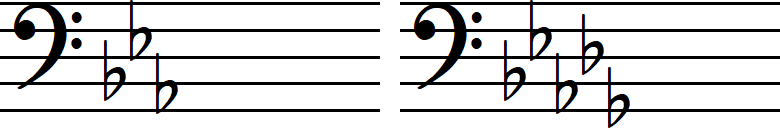
♭の調号を探る
上記は♭が3つと5つの調号です。同じように何の調になるのかを、探る方法があります。これら2種類の♭の調号を、例に挙げて説明していきます。
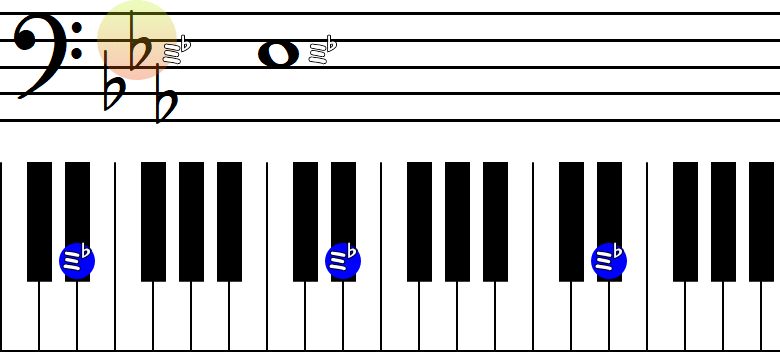
♭3つの長調
最後から2番目に書かれた♭に注目しましょう。ミの高さに♭があるので、つまりはミ♭と考えてください。そのミ♭がそのまま長調の主音になるので、♭3つの調号は変ホ長調と判断できます。
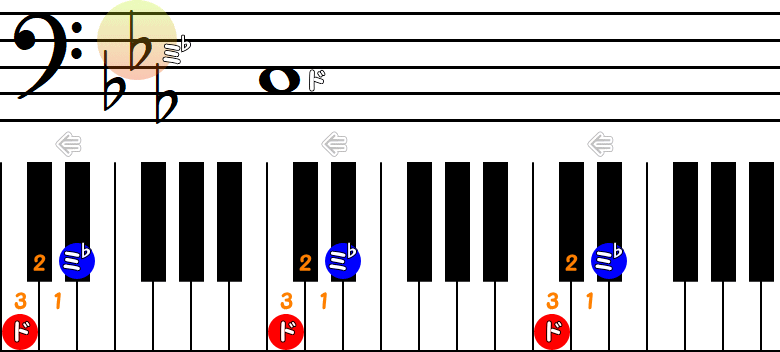
♭3つの短調
次は♭3つの短調を求めますが、これは#の時と同じ方法です。長調の主音であるミ♭から、半音3つ下はドで、そのドが短調の主音になり、♭3つの調号はハ短調という事にもなります。
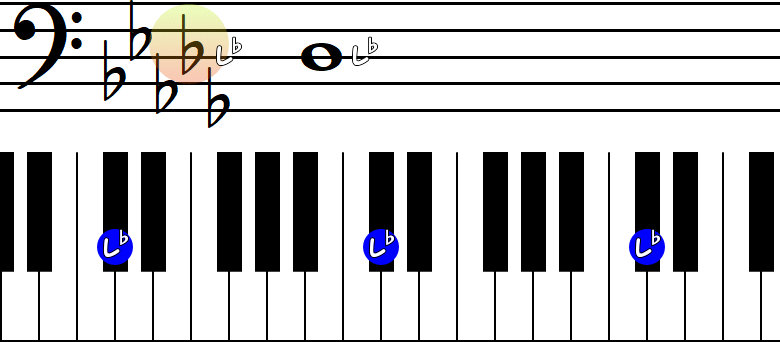
♭5つの長調
最後から2番目に書かれた♭はレにあり、つまりはレ♭と考えましょう。そのレ♭が長調の主音になるので、♭5つの調号は変ニ長調と判断します。
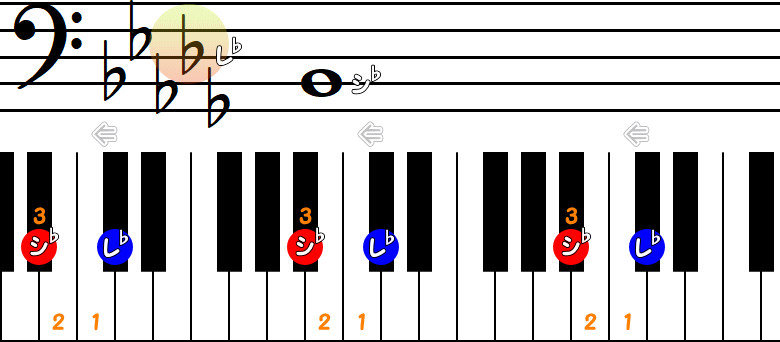
♭5つの短調
次は♭5つの短調を求めます。長調の主音であるレ♭から、半音3つ下はシ♭です。そのシ♭が短調の主音になるので、♭5つの調号は変ロ短調という事にもなります。
♭の調号の覚え方まとめ
- 最後から2番の♭が長調の主音。
- 長調の主音から半音3つしたが短調の主音。
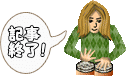
- 調を表すには調号を使う。
- 調号は#と♭に分けられる。
- 調号には昔ながらの覚え方がある。